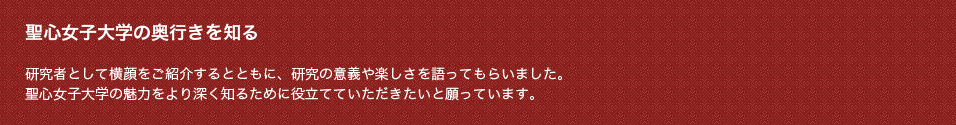
聖心女子大学の奥行きを知る
研究者として横顔をご紹介するとともに、研究の意義や楽しさを語ってもらいました。聖心女子大学の魅力をより深く知るために役立てていただきたいと願っています。



| 研究テーマ | : | 芸術制作を主とした創造行為や芸術作品を中心に形成される共同体に関する美学的研究。 |
|---|---|---|
| 著書 | : | (特にありません) |

『パイドロス(岩波文庫)』
著者:プラトン
出版社:岩波書店
この対話編は、古代ギリシアで流行っていたレトリック(日本語では「弁論術」や「修辞学」といいますが)を取り上げ、どういう言葉を相手に投げかければいいのかを、ものごとの真理や他者の魂への配慮と関係づけながら考察しています。大学3年のゼミで、最初に読んだのはギリシア語の原書でしたが、今でも演習のテキストにしたり、学生に語りかけるときに生かしています。

出身は東京大学文学部第1類美学芸術学専修課程。高校時代からディスカッションをメインにしたやや哲学系のクラブに所属し、絵画や建築にも興味を抱いていたという上石学先生。「わざわざ東大で就職に不利な文学部、しかも美学芸術学とは」という声も聞こえてきそうだが。「最初は建築家に憧れていましたが、理系科目が苦手なので文系へ。それなら経済や法律より芸術系の方が面白いと思い、文学部で美学芸術学という道を選びました」。絵画への興味と美学のつながりには何の矛盾もないが、そもそも美学や芸術と哲学とはどこでどう交わるのか。上石先生は次のように説明する。「哲学は論理的なもの、芸術は感覚的なもの、という分け方をすると確かに相反する矛盾した組み合わせのようですが、それは現代人の感覚です。かつては美について、それをとらえる主観的なものの感じ方ではなくて、客観的なものの特質(例えば、シンメトリーや調和)を美の根拠と考えていたり、芸術作品に接するときに、今のように感性や感覚ではなくて、理性や知識が強く求められている時代も長く続いていました。美や芸術の体験は、もちろん文字通りに『論理的』というわけではありませんが、理性的なものを含め、もっと全体的・総合的なものだと思います。美学は美や芸術を扱いますが、だからといって哲学的でなくなるわけではないのです。そもそも美学について言えば、もともと人間とは何なのか、人間は何を求め、何に心地よさを感じるか、という問いがベースにあって、それを探求することは想像以上に論理的な世界です」。
芸術作品の評価には創り手(作品)と自分との間に生まれた共感が重要な役割をもつことがあるが、そのつながりがどの時点で生まれたのかをつきつめていけば、自分がその作品のどこに惹かれたのかがわかる。それはつまり自己理解の一つと言っていいだろう。
「何の予断も持たずに絵の前に立ち、これは良いと感じたら、何が良いのか自分に問いかけてみます。そこで出た答え、たとえば青い色に惹かれたら、青が好きな自分自身に気がつく。さらに、それがどんな青なのか、その青について自分は何を感じたのか、考えたのかを問うてみる。それが美学や芸術を通して自己と対話する術を身につけるということなのです」。

考えてみれば、「良い」とか「好き」とか、そういう感覚自体が自分の中で成熟していないケースがある。ファッションやインテリア、ライフスタイル、人間関係、大学や将来の進路も、自分が「良い」と思って選べばいいが、ついつい他人の評価や判断に頼ってしまうケースがあることも否定できない。「だから、好き嫌いがはっきり言えるようになることも、美学を通して身につく大きなスキルなのです。もちろん、これは個々の感性に判断を任せることでもあり、ちゃんと良いと言えるかどうか自信がない人もいるでしょう。でも、本当に良くできた芸術やものを、人間は自然に感じ取る力を持っているんですよ」。
演習では昨年から他の教員と協力し、新しい取り組みとしてビデオ制作を導入した。「スキルもメソッドもないのにスタートしました(笑)。作品づくりの共同作業の現場を体験したり、制作活動が共同体の形成にどう役立つのかも試してみたくて、ちょっとしたトライですね」。こうしたチャレンジも「美学芸術学」ならではのもの。絵画などの芸術作品から哲学へとアプローチできる点は大きなアドバンテージだが、それは同時に諸刃の剣だと上石先生は感じている。「見せるものが多いですから、“入り口”はすごくとっつきやすいと思います。でも、よく注意しないと“見てわかりやすいところ”ばかりに食いつくようになります。そうなると次のステップに進むのが大変になります。人間って面白いとそこしか見なくなるわけで、地道な努力とか成長を促す苦痛をいかに盛り込むかも今後の課題です」。

上石先生が研究をはじめるきっかけとなった本
『名画を見る眼』
1人の研究者として今、最も関心を持っているのはフランスの哲学者で劇作家でもあるガブリエル・マルセル。キリスト教的実存主義者でもあり、哲学と演劇、芸術と宗教など多様なアプローチが考えられる研究対象だ。「演劇の脚本を書いていると、登場人物が勝手に話し始めるそうなんです。それはつまり、自分の中に他者が住んでいるわけですよね。“自己と他者”とか“自己とそれを超えたもの”という宗教的な人間観を作品づくりの中で体験しているとも言えます。芸術と哲学、それと神さまや信仰は結構、深い関係があります」。
学生とのコミュニケーションで心がけているのはフラットな関係。「あまり教員と学生という意識が強いと、学生から得るものがなくなってしまう。瑞々しい感性とか、自分にないもの、失ってしまったものを吸収できることが、ゼミを主宰する大きなメリットですね(笑)」。そんな上石先生の指導における持論は「結果や目的は考えさせない」だ。
「純粋な知的好奇心が一番です。だから学生には結果とか目的とか、初めからあまり考えすぎない方がいいと言っています。それを意識して勉強しても得るものはあまりないですから。たとえば、卒業論文に、初めには想像もできなかったことを書いている自分を発見したという学生がいましたが、それは多分、簡単に見通しのきく目標や目的でやってこなかったから生まれた結果だと思うんです」。最初に結果や目的を考えると、そこまでしかたどり着けない。いかにも哲学的な見方だが、こうした言葉のやりとりが上石先生の持ち味かも知れない。上石先生自身が感じる「哲学」の面白さは「自分自身が納得できる言葉を使って何かを説明できた時の喜び」。とかく「説明不要」のわかりやすさに走りがちな現代だが、ここではできるだけ説明したがる人、説明を聞きたがる人を育てたいと語る。「芸術のいいところは、押しつけがましくならずにそういう会話(説明)ができるところ。経済や政治の話じゃそうはいきません。是非ここで、それぞれが生き生きと“説明できるモノ”を見つけてください」。
![]()
